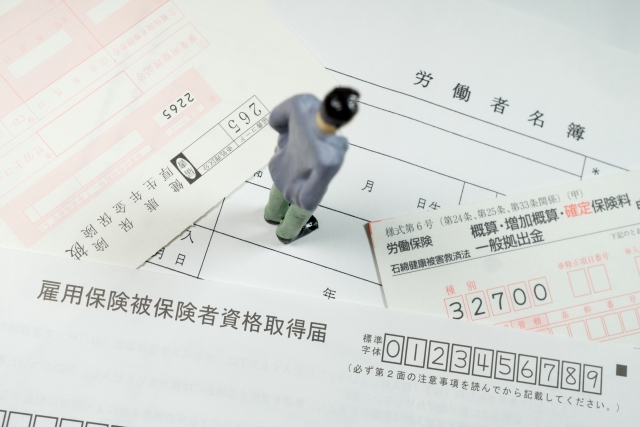事業を開始して、労働者を雇い入れたときは、事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きをしなければなりません。
「労働保険?社会保険?何が違うの?」
「アルバイトのA君も、保険に入れないといけないの?」
と疑問に思う方も多いかと思いますので、基礎から順に整理していきます。
従業員を雇用するということは、事業主として法律上の様々な責任を負うことでもあります。特に、従業員を万が一のリスクから守る「労働保険」への加入は、会社に課せられた最初の、そして最も重要な義務の一つです。
「忙しいから後で…」と手続きを怠ってしまうと、法律違反になるだけでなく、いざという時に大切な従業員を守れないという事態にもなりかねません。
この記事では、まず最初に理解しておくべき「労働保険」の基本を、分かりやすく解説します。
この記事を読み終える頃には、
・労働保険の全体像
・「労災保険」と「雇用保険」の役割の違い
・誰を保険に加入させる義務があるのか
といった、最初の疑問がスッキリ解消されているはずです。
労働保険とは?【結論:労災保険と雇用保険のセットです】
労働保険とは、「社会保障制度の一部」ではありますが、狭義の「社会保険(健康保険・厚生年金保険)」とは別制度で、具体的には「労災保険(労働者災害補償保険)」と「雇用保険」という2つの保険をまとめた総称です。
一方、狭義の「社会保険」は健康保険と厚生年金保険を指し、労働保険とは区別されます。これらの保険は、加入要件や手続きがそれぞれ異なります。
労災保険と雇用保険の2つの保険は、保険金が支払われる(保険給付)場面はそれぞれ異なりますが、保険料の納付手続きなどでは「労働保険料」として一体的に取り扱われます。
労災保険と雇用保険、それぞれの目的と役割
では、2つの保険はそれぞれどのような目的を持っているのでしょうか。
労災保険:仕事中や通勤中のケガ・病気などへの備え
労災保険は、労働者が仕事が原因で(業務災害)、または通勤の途中で(通勤災害)、ケガをしたり、病気になったり、障害が残ったり、最悪の場合亡くなってしまった(負傷、疾病、障害又は死亡)際に、国が治療費や生活費などを補償してくれる制度です。
代表的な給付には次のようなものがあります。
・療養(補償)等給付:治療等の現物給付、治療費等の現金給付
・休業(補償)等給付:働けない間の賃金補償
・傷病(補償)等年金:長期間の療養の場合に年金として補償
・障害(補償)等給付:治療後も体に障害が残った場合の年金や一時金
・介護(補償)等給付:介護費用としてかかった費用が支給
・遺族(補償)等給付:遺族の生活を支える年金や一時金
・葬祭料(葬祭給付):葬儀費用の一部
・二次健康診断等給付:
定期健康診断で脳・心臓疾患に関連する異常が見つかった場合の二次健診費用
また、被災した労働者がスムーズに社会復帰できるよう支援することも目的としています。
【重要ポイント】「労災保険」と「健康保険」の使い分け
このように、労災保険が適用されるのは、あくまで「業務上」または「通勤途中」の災害に限られます。
では、プライベートの時間に遊んでいてケガをしたり、仕事とは全く関係のない病気にかかったりした場合はどうなるのでしょうか。
こうした仕事以外が原因のケガや病気(私傷病といいます)については、労災保険ではなく、皆さんが普段、病院の窓口で提示する「健康保険」が適用されます。
「仕事中・通勤中なら労災保険」「私傷病なら健康保険」と、この使い分けを正しく理解しておくことが大切です。
参考情報:厚生労働省「労災補償」
雇用保険:失業したときなどの生活の支え
雇用保険は、労働者が失業して収入がなくなった場合や、育児・介護などで働き続けることが困難になった場合などに、生活の安定を図り、スムーズな再就職をサポートするための制度です。
一般的に「失業手当」として知られている給付(基本手当)は、この雇用保険から支払われます。
代表的な給付には次のようなものがあります。
・基本手当:いわゆる失業手当
・育児休業給付:育児休業中、育児短時間勤務中などの賃金低下を補填
※出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金はこども未来戦略に基づき、令和7年4月1日に創設されました。
・教育訓練給付:一定の教育訓練を受講・修了したときに受講費用の一部が支給
雇用保険は生活のセーフティネットとして重要な役割を果たしています。
参考情報:厚生労働省「雇用保険制度」
労働保険の適用事業
労働保険(労災保険・雇用保険)の保険関係が成立する事業を「適用事業」といいます。
パート、アルバイトや契約社員、派遣社員などを含む労働者を1人でも雇用していれば、原則として労働保険の適用事業となります。(農林水産の一部の事業を除く)
適用事業となった場合、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
誰が労働保険の対象になるの?
次に、どのような人がそれぞれの保険の対象となるのかを見ていきましょう。
労災保険の対象者:原則すべての労働者
労災保険の対象となる労働者の範囲は、労働基準法上の「労働者」と同じです。
つまり、アルバイト、パート、外国人労働者など、雇用形態や国籍にかかわらず、会社に雇用されて賃金を受け取るすべての人が対象となります。
一方で、個人事業主や法人の代表取締役、同居の親族などは、原則として労働者に含まれないため、労災保険の適用は受けません。
特別加入制度
労働者以外でも、一定の要件を満たす場合には、労災保険に任意加入できる「特別加入制度」があります。
その業務の実態や、労災の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる者に対して、任意で加入できます。
中小企業の雇用主やその家族従事者、一人親方その他の自営業者、特定作業従事者などで、例えば、個人タクシー事業者、家政婦(夫)、農業従事者、建設業や林業のひとり親方等、介護作業従事者、柔道整復師、芸能関係者、アニメーターなど多岐にわたります。
令和6年11月からは、特定受託事業に従事する者(いわゆるフリーランス)も特別加入の対象に追加されています。
参考情報:厚生労働省「労災保険への特別加入」
雇用保険の対象者:週20時間以上などの条件あり
雇用保険の対象者(被保険者)となるには、以下の2つの要件を両方満たす必要があります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・31日以上の継続的な雇用が見込まれること
・昼間部の学生ではない
(ただし、通信制、夜間、定時制の学生や、休学中の学生、卒業後も引き続き同じ会社で勤務する予定の学生などは加入対象となります)
この条件を満たせば、アルバイトやパートといった雇用形態にかかわらず、雇用保険に加入する義務があります。
次回は「労働保険の加入手続きについて」をご説明します。